
M&Aノウハウ
最終更新日: 2025/2/13
法人の廃業・清算の手続きと流れ、費用や注意点について徹底解説
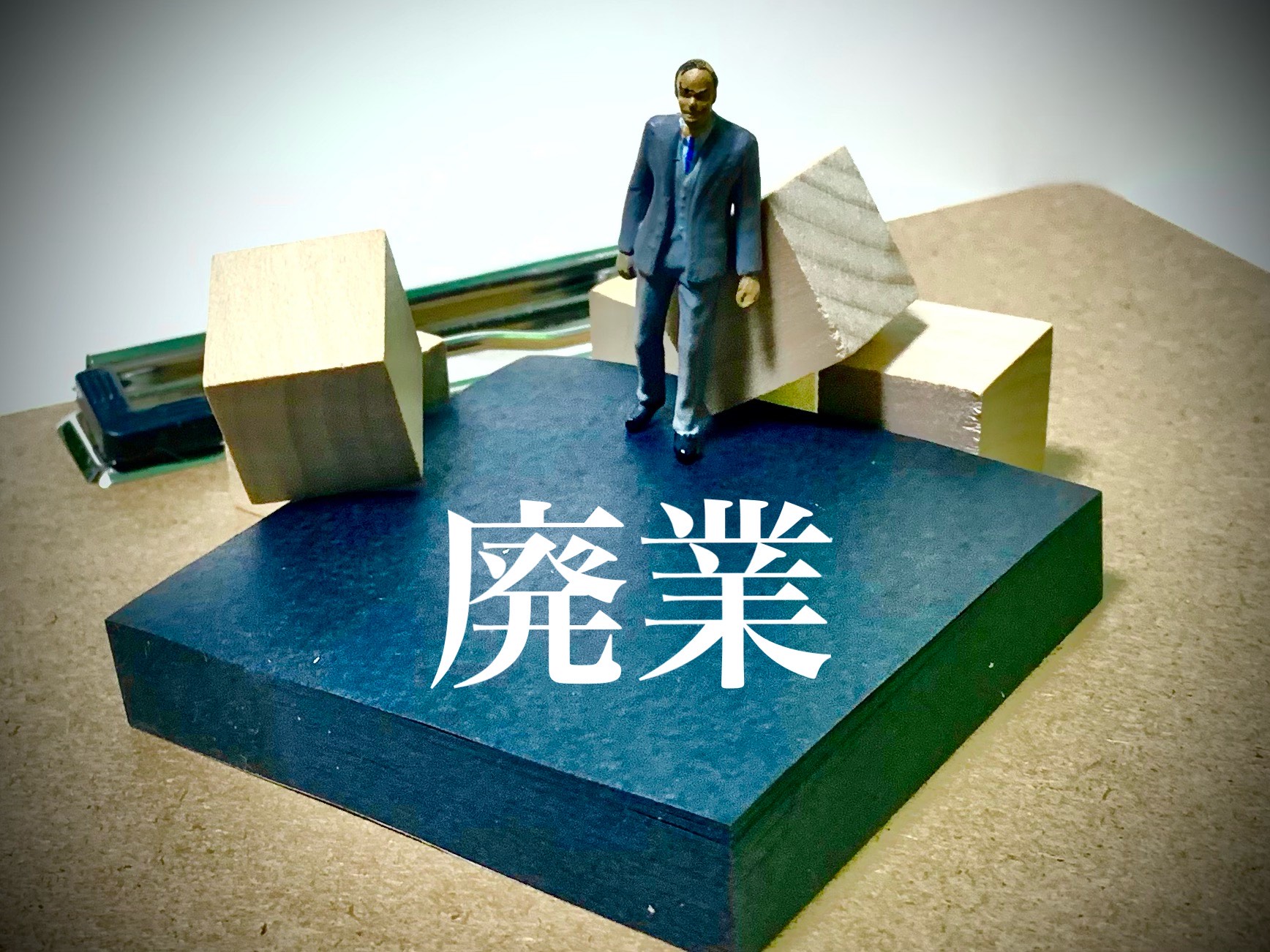
「法人の廃業・清算における手続きの流れや、かかる費用を知りたい」
「廃業・清算する上での注意点を知りたい」
このようにお考えではありませんか?
本記事では、法人の廃業・清算について手続きの流れや費用、注意点を解説します。
あわせて、解散・破産・清算といった混同しやすい用語との違いも解説するので、廃業・清算を検討する際の参考にしてください。
弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
法人の廃業とは
廃業とは、経営者が自らの判断で会社経営を終了することです。
同じような言葉に「倒産」がありますが、倒産は資金繰りなどの問題で会社の経営ができなくなることを指します。
廃業は、業績の悪化を理由とするほか、後継者不在で事業を継続できない場合の選択肢としても選ばれています。
帝国データバンクによる「全国企業『休廃業・解散』動向調査(2024年)」によると、2024年の休廃業・解散は6万9019件にのぼり、前年比1万件の大幅増となりました。
休廃業時における経営者の平均年齢は過去最高となる71.3歳であり、経営者の高齢化が進む中、後継者不在のまま廃業に至るケースも少なくありません。
なお、廃業の際に資産や負債は整理され、法人格が消滅するため、一度廃業すると元には戻せません。
また、廃業するには会社法などの規定に基づき各種手続きを進めなければならず、周囲に相談し、協力を得ながら計画的に進めることが重要です。
解散・清算・破産との違い
廃業と混同しやすい用語として、解散・清算・破産があります。ここでは、解散・清算・破産について解説します。
解散とは
会社の廃業には、解散と清算の2つのプロセスが必要であり、解散は会社の資産を清算して消滅させるための手続きのスタート地点です。
会社を解散するには、以下の会社法で定められた解散事由を満たす必要があります。
- 定款が定める存続期間の満了
- 定款が定める解散事由の発生
- 株主総会の決議
- 合併により会社が消滅する場合
- 破産手続き開始の決定
- 裁判所による解散命令
- 休眠会社のみなし解散の制度
後継者不在や資金繰り・業績の悪化などにより廃業する場合は、「株主総会の決議」あるいは「破産手続き開始の決定」のいずれかが解散事由となります。
清算とは
清算とは、会社が解散した後に資産や負債を整理して、残余財産を分配する手続きのことです。
会社を廃業する際は解散を行った後、清算を行うことで会社が消滅します。
清算には、通常清算と特別清算の2つがあり、特別清算でも債務の完済が難しければ破産手続きを行います。
ここでは、通常清算、特別清算、破産についてそれぞれ説明します。
通常清算
通常清算は、会社に残った資産で負債をすべて弁済できる場合に行われる清算手続きです。
保有資産だけでは債務を支払えない場合でも、売掛金の回収や在庫の換価による資産で賄える場合は通常清算が適用されます。
すべての弁済を終えた際に残余財産がある場合は、株主に配当を行い清算手続きを完了します。
通常清算においては、選任された清算人を主体として手続きが行われ、裁判所は関与しません。
特別清算
特別清算は、負債が資産を上回っている場合や、負債が資産を上回る疑いがあるケースで用いられます。
通常清算は会社の手続きだけで完了しますが、特別清算は裁判所の監督のもとで進められます。
なお、特別清算でも債務の完済が難しい場合は、破産法に基づく破産手続きが行われます。
破産と比較して、特別清算には以下のメリット・デメリットがあります。
特別清算のメリット | ・費用を比較的抑えられる ・手続きが簡易 ・自社で選任した担当者に手続きを依頼できる ・「破産」よりもネガティブなイメージが少ない |
|---|---|
特別清算のデメリット | ・一定以上の債権者からの同意が必要 (破産よりもハードルが高い) ・会社法に基づくため、株式会社以外では利用できない |
特別清算において債務の完済が難しい場合は、債権者との協定あるいは和解により債務を減額したうえで完済します。
破産
破産は、債務超過などで事業の継続が困難になった際に裁判所へ破産手続きを申し立て、破産法に基づいて進められる手続です。
破産手続きによって会社の資産は換金され、債権者への配当に充てられます。なお、支払いきれない債務については、会社の消滅とともに支払い義務もなくなります。
特別清算は債権者への返済を前提としているのに対し、破産は借金の返済を前提としないことは大きく異なる点です。
株式会社の廃業・清算の流れ
株式会社の廃業プロセスは、解散・清算・清算結了という流れであり、具体的なフローは以下のとおりです。
- 株主総会の開催・解散決議
- 解散登記と清算人の登記
- 各機関へ解散の届出
- 財産目録・貸借対照表の作成
- 解散確定申告
- 官報公告・個別催告
- 清算と残余財産の分配
- 清算確定申告書の提出
- 決算報告書の作成・承認
- 清算結了の登記
それぞれ説明します。
1.株主総会の開催・解散決議
会社を廃業するには、まずは会社を解散し、営業を停止します。
解散するには、会社法で規定された解散事由を満たす必要があり、株主総会の特別決議が必要です。
特別決議では、発行済株式総数の過半数の株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得て解散を決議します。
2.解散登記と清算人の登記
会社廃業の際は財産の清算が必要となるため、株主総会では「清算人」の選任も行います。
清算人となる人は定款で定められている場合もありますが、とくに指定されていなければ、解散時の代表取締役が清算人となるケースが多いでしょう。
選任した清算人は法務局で登記手続きを行う必要があり、通常、清算人選任登記は解散登記と同時に行われます。期限は解散日から2週間以内です。
3.各機関へ解散の届出
解散登記が完了した後、各機関へ税務関係の届出を行います。
法人税については税務署、法人住民税・法人事業税は都道府県や市区町村役場の税事務所に解散届を提出します。
また、許認可を受けている場合は、許認可庁に解散の届出が必要です。
4.財産目録・貸借対照表の作成
廃業手続きでは、清算手続きに入る前に、財産の現金化や債務の支払いの基となる決算書類を作成します。
具体的には、清算人が財産目録および貸借対照表を作成した後、株主総会にて承認を受けます。
5.解散確定申告
決算書類の作成・承認が完了したら、解散事業年度の確定申告を実施します。
なお、解散事業年度とは、事業年度の開始日から解散日までを指します。
解散確定申告の期限は、解散日から2か月以内です。
6.官報公告・個別催告
廃業に伴う清算を行うためには、債権者からの申し出が必要であり、会社解散後は法律に基づき政府発行の官報に解散公告を掲載することが定められています。
官報に公告を掲載し、会社が解散したことを知らせるとともに、一定期間内に債権の内容を届け出るよう求めます。なお、官報での解散公告は2か月以上の掲載が必要です。
また、会社で把握している債権者には個別に通知を送り、債権の届出を依頼します。
7.清算と残余財産の分配
官報への公告掲載期間が終了したら、会社の財産を整理し、残余財産を確定します。
具体的には、不動産や有価証券、在庫などの会社の資産を売却してお金に換え、債務の支払いを行います。
なお、集めた資金で債務を全額返済できない場合は、特別清算または破産手続きへの移行が必要です。
一方、債務を完済した後に会社の資産が残っている場合は、株主へ分配します。
分配の際は、負債だけでなく、税金や社会保険料もすべて支払ったうえで財産を分配する必要があります。
8.清算確定申告書の提出
清算と残余財産の処理が完了したら清算確定申告書を提出し、残余財産確定事業年度について確定申告を行います。
期限は、残余財産が確定した日から1か月以内です。
9.決算報告書の作成・承認
清算が終了したら決算報告書を作成します。
決算報告書が株主総会において承認されると法人格が消滅し、会社は廃業となります。
10.清算結了の登記
株主総会で決算報告書の承認を得た後、法務局にて2週間以内に清算結了登記の手続きを行います。
なお、清算結了の登記が完了すると、会社の廃業手続きも完了します。
廃業・清算にかかる期間
会社を廃業するためには、法律で定められた手続きを、一つずつ順を追って進める必要があります。
そして、手続きのひとつである官報公告は「2か月以上」と期間が定められているため、清算結了までには最低でも2か月以上はかかります。
実際には、会社が所有する不動産の換価や債権者への支払いに時間を要するケースも多く、廃業手続きを進める際には期間も考慮して十分に計画を立てることが大切です。
廃業・清算にかかる費用
廃業・清算にかかる費用には、おもに以下のようなものが挙げられます。
項目 | 費用 |
|---|---|
登録免許税 | 解散登記:30,000円 清算人登記:9,000円 清算結了登記:2,000円 |
官報公告費用 | 1行につき3,589円 30,000〜40,000円が目安(9~11行) |
登記事項証明書の発行手数料 | 数千円 |
専門家への依頼費用 | 数万~数十万円 |
在庫・設備の処分費用 | 数万〜1,000万円以上 |
不動産の原状回復費用 | 坪あたり数万~10万円 |
廃業・清算の際は、各種登記や証明書の費用、在庫・設備の処分費用、借りている物件の原状回復費用などがかかります。
実際は、会社の事業形態や在庫の種類・量、機械や設備の種類・使用年数などによってかかる費用は異なります。
廃業・清算の注意点
会社の廃業・清算を行う際には、おもに以下のような注意点があります。
- 従業員が職を失う
- 独自のビジネスモデル・ノウハウなどが失われる
- 取引先にも影響する
- 借金が残る可能性がある
- みなし配当で税金がかかる場合がある
それぞれ説明します。
1.従業員が職を失う
廃業すると会社自体がなくなるため、一緒に働いてきた従業員は解雇となり、職を失ってしまいます。
例えば、M&Aで会社を売却した場合は従業員の雇用を維持できるので、雇用を維持できない点は廃業の大きなデメリットと言えます。
廃業による従業員の生活への影響を最小限に抑えるためにも、廃業を伝える時期を適切に選び、再就職がスムーズに行えるようサポートするなど、できる対策を十分に講じることが大切です。
2.独自のビジネスモデル・ノウハウなどが失われる
廃業すると会社は消滅するため、これまで確立してきた独自のビジネスモデルやノウハウ、ブランドがすべて失われてしまいます。
独自のビジネスモデル・ノウハウといった見えない資産が失われることは、業界全体の技術力や、地域経済が衰退する要因にもなります。
さらに、今まで自社の商品やサービスを利用していた顧客にも影響を及ぼすでしょう。
3.取引先にも影響する
廃業・清算による影響は、取引先にも及びます。
例えば、自社が廃業することで、取引のあった仕入れ先企業は売上が減少してしまいます。結果、場合によっては仕入れ先企業が連鎖的に倒産する可能性も考えられるでしょう。
突然廃業すると取引先にも大きな影響を及ぼすため、なるべく早い段階で通達し、円滑に取引を終了できるよう努めることが大切です。
4.借金が残る可能性がある
廃業しても、会社の借金を経営者が個人的に返済する必要はありません。
ただし、会社の資金を金融機関から借入する際に連帯保証人となっている場合は、経営者に返済する義務が残ります。
結果として、経営者が負担を負うことになり、個人資産を切り崩さざるを得なくなるため注意が必要です。
5.みなし配当で税金がかかる場合がある
会社の廃業・清算の際、残余財産の分配において受け取った金額が出資した金額より大きかった場合、増加した部分はみなし配当として課税されます。
非上場企業から受け取るみなし配当は、総合課税の対象です。累進課税制度により他の所得と合算した所得額に応じて最大49.44%の税率が適用されるため、予想外の高い金額の税金が課される可能性があります。
一方、M&Aを行った場合は、株式譲渡益に対して一律20.315%の税率が適用されるため、税金上はM&Aが有利と言えます。
さらに、M&Aには従業員の雇用維持や取引先との関係継続などのメリットもあり、状況によっては廃業ではなくM&Aを選択することも有効です。
なお、弊社のシェアモルM&Aでは、豊富な経験と知識によりM&Aをご支援いたします。
廃業以外の選択肢としてM&Aをご検討の方は、シェアモルM&Aにお問い合わせください。
まとめ:廃業・清算は専門家の意見も取り入れて慎重に判断しよう

今回は、法人の廃業・清算について、解散・破産・清算といった混同しやすい用語との違いを解説するとともに、手続きの流れや費用、注意点を解説しました。
廃業・清算する際は、会社法などの規定に則り各種手続きを進めなければならず、周囲の協力を得ながら計画的に進める必要があります。
近年、経営者の高齢化が進む中、後継者不在のまま廃業・清算に至るケースも少なくありません。しかし、廃業には従業員の失業や取引先への影響など注意すべき点もあります。
後継者問題の解決策には、M&A・事業承継も選択肢の一つとして有効です。廃業・清算を検討する際は、専門家の意見も取り入れて、慎重に判断しましょう。
なお、弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また、シェアモルM&AのコラムにはM&A・事業承継関連の記事も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
シェアモルM&Aでは無料相談を実施しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
最終更新日: 2025/2/13
まずは無料相談
ミーティング時に貴社とシナジーのあるクライアントの概要をお伝えいたします。
無料で事業価値の算定も可能でございますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
監修者
齋藤 康輔シェアモル株式会社 代表取締役
東京大学教養学部基礎科学科在学中に、半導体(シリコン)のシミュレーションを専攻する傍ら、人材会社にてインターン。
インターン中に人材会社向け業務システムを開発し、 大学卒業後の1年間、上記人材会社にて勤務後、 共同出資で2007年3月に上記システム「マッチングッド」を販売する会社、 マッチングッド株式会社を設立。
12年の経営の後、2019年1月に東証プライム上場企業の株式会社じげんに株式譲渡。
2019年9月、売却資金を元手に、シェアモル株式会社を設立。
自身のM&Aの経験から、買い主と売り主の間での情報の非対称性や、 M&A仲介会社が出している付加価値に疑問を感じ、 自身が思わず依頼したくなるような、 付加価値の高いM&A仲介サービスを提供したいと強く思い、 IT技術をフル活用したM&A仲介事業「シェアモルM&A」をスタート。
現在はシェアモルM&Aと、SEOに強い文章をAIが作成する「トランスコープ」を展開中。


