
M&Aノウハウ
最終更新日: 2025/3/4
第三者割当増資とは?目的や手続き、M&Aとの違いを徹底解説
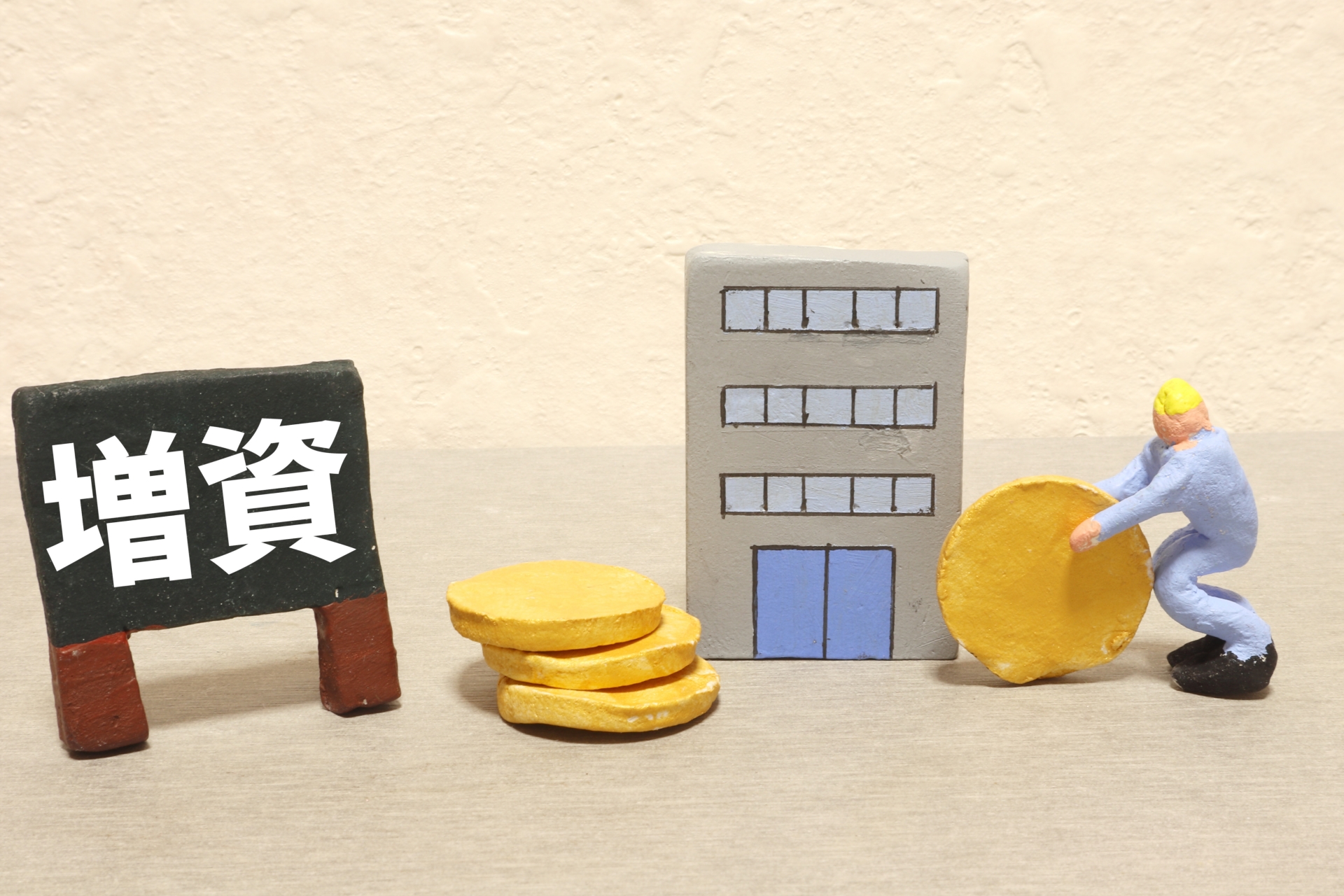
「第三者割当増資の仕組みや目的を知りたい」
「第三者割当増資を行うメリット・デメリットを知りたい」
このようにお考えではありませんか?
本記事では第三者割当増資の仕組みや目的、手続きの流れ、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。
資金の確保や他社との連携強化など、経営戦略の選択肢として第三者割当増資を検討する際の参考にしてください。
なお、M&Aについては、M&Aに特化したアドバイスが可能なシェアモルM&Aにご相談ください。
弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
第三者割当増資とは
第三者割当増資は、会社が資金を調達する手法のひとつです。特定の第三者に対して有償で新株を発行し、対価として資金を得ます。
特定の第三者は個人・法人を問わず、株主にも限りません。ただし通常は、取引先や取引金融機関、自社の役職員といった関わりのある相手に発行することが一般的です。
第三者割当増資は、公募増資や株主割当増資と並ぶ有償増資の一種です。
公募増資は、株式の引き受けを募る際に既存株主か新規株主かを問わない点で、第三者割当増資と類似しています。募集の対象が広範な第三者に及ぶため、資金調達の規模を大きくしやすい反面、手続きが煩雑になりやすく費用負担が増えるのがデメリットです。
株主割当増資は既存の株主向けに実施される増資方法であり、保有株数に応じた割合で新株が付与されるため、株主の保有割合が変わりません。一方で、出資者が既存株主に限られるため、必要な資金を十分に調達できない可能性があります。
目的
第三者割当増資には、おもに以下の3つの目的があります。
▪️資金調達
第三者割当増資は、事業拡大や新規事業の立ち上げなどで資金を要する際、資金調達の手段の1つとなります。会社の成長に賛同する相手に株式を発行して資金を集める手法であり、資金調達の手段として有効です。
▪️他社との関係強化
第三者割当増資により資本関係を構築することで、他社との協力関係を強化できます。単なる業務提携よりも密接な関係を構築でき、経営への参画や財務支援などが可能になります。
▪️M&A・事業承継
第三者割当増資を実施すると、買収先に新たな株式を発行し、多くの議決権を付与できます。買収先が株式や議決権を取得する一方で、既存株主の持株を譲渡するわけではないため、原則として所得税の課税対象にはなりません。
M&Aとの違い
第三者割当増資とM&Aは、どちらも企業の成長や事業戦略の一環として活用される手法ですが、目的や手続き、資金の流れなどに違いがあります。
例えば、M&Aは、企業の経営権を移転・統合することで、成長戦略を実現します。なお、株式譲渡では売却代金が旧株主に支払われるため、資金調達の手段としては適しません。
一方、第三者割当増資は特定の第三者に新株を引き受けてもらうことで、資金調達やパートナーシップの強化を図ることを目的としています。新たに発行された株式の代金は企業に直接入るため、財務基盤の強化につながります。
第三者割当増資のメリット
第三者割当増資のメリットについて、売り手企業、買い手企業それぞれに分けて解説します。
売り手企業のメリット
売り手企業のメリットは、以下の5つです。
- 財務基盤を強化できる
- 返済義務がない
- 新株主を選べる
- 買い手企業との関係強化を図れる
- 信用力の向上につながる
それぞれ説明します。
1.財務基盤を強化できる
第三者割当増資のもっとも大きな利点は、企業に直接、資金を投入できる点です。
新たに株式を発行して資金を確保できるため、財務基盤の強化につながり、資金繰りの安定が期待されます。また、公募増資に比べて手続きが少なく、スピーディーな資金調達が可能です。
2.返済義務がない
銀行からの借り入れや社債の発行では、元本と利息の返済が必要ですが、第三者割当増資によって得た資金には返済義務がありません。
事業で得た利益は配当金として株主に還元できますが、銀行融資のような返済義務がないため、事業の成長に集中できます。
3.新株主を選べる
3つ目のメリットは、新株主を選べることです。
例えば、公募増資では新株の引受先を任意に指定できないため、意図しない企業や人物が株式を取得し、一定の議決権を持つ可能性があります。
しかし、第三者割当増資なら株式を発行する相手を選べるため、意図しない株主の参入を防ぎながら、戦略的な資本提携を進められます。
4.買い手企業との関係強化を図れる
第三者割当増資によって買い手企業と資本関係を築くことで、強固な関係が生まれます。
一般的に、第三者割当増資では取引先や金融機関が新株を引き受けるケースが多く、株式や議決権を持ってもらうことで関係性の強化につながり、両社の事業の相乗効果が期待できます。
株式を保有することで配当金や売却益を得るインセンティブが生まれ、発行会社の成長を後押しし、取引の拡大にも繋がるでしょう。
5.信用力の向上につながる
第三者割当増資を実施すると会社の資本金が増加し、信用力の向上が期待できます。
信用力が向上すると資金調達がしやすくなり、調達した資金を活用して事業規模の拡大や新規事業への進出が可能になります。
買い手企業のメリット
買い手のメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
- 売り手企業との関係を強化できる
- 連結決算での利益取り込み効果を期待できる
- 100%買収と比べてリスクを回避できる
それぞれ説明します。
1.売り手企業との関係を強化できる
新株を引き受けることで売り手企業と資本関係を築き、関係性を強化できます。さらに、関係が深まることで両社の事業における相乗効果が生まれやすくなり、より密接な協力体制を構築することが可能になります。
2.連結決算での利益取り込み効果を期待できる
第三者割当増資により取得対象の企業を連結子会社化すると、企業の利益や資産をグループ全体の決算に反映でき、収益基盤の強化につながります。
また、損益通算が可能になり、グループ内で柔軟に資金繰りができるため、財務戦略の選択肢が広がるメリットもあります。
3.100%買収と比べてリスクを回避できる
第三者割当増資で議決権を得る場合、他の株主が存在するため、100%買収と比べて経営責任やリスクを回避しやすくなります。そのため、財務リスクを抑えつつ、対象企業との関係を構築できます。
第三者割当増資のデメリット
続いて、第三者割当増資のデメリットについて、売り手企業と買い手企業に分けて解説します。
売り手企業のデメリット
売り手企業のデメリットには、以下の3つがあります。
- 既存株主の持株比率が低下する
- 既存株主が直接資金を受け取れない
- 税負担が増える可能性がある
それぞれ説明します。
1.既存株主の持株比率が低下する
第三者割当増資では、新しく株式を発行することで既存の株主の持株比率が下がり、価値が目減りする可能性があります。結果として、株価の下落や株主離れを招くこともあるでしょう。
また、新株の発行価格が適正でない場合、既存株主に不利益をもたらすリスクがあります。とくに、市場価格よりも低い「特に有利な価格」で発行する際は、株主総会で新株の発行価格が適正でない理由を説明して特別決議を経る必要があるため、慎重な対応が求められます。
2.既存株主が直接資金を受け取れない
第三者割当増資では、新しく発行された株式の代金は発行企業に支払われるため、既存株主が直接資金を受け取ることはできません。
3.税負担が増える可能性がある
基本的に、第三者割当増資で税金は発生しませんが、資本金が増えることで将来的な税負担が増加する可能性があります。
例えば、東京都では資本金1,000万円以下では都道府県民税が2万円ですが、1,000万円超から1億円以下になると5万円に引き上げられます。
また、資本金1億円以上になると、中小法人向けの税制優遇が受けられなくなり、法人税の軽減税率が適用されなくなることもデメリットです。
買い手企業のデメリット
買い手側のデメリットには、以下の2つが挙げられます。
- 議決権は100%取得できない
- 株式譲渡に比べ多額の資金が必要
それぞれ説明します。
1.議決権は100%取得できない
第三者割当増資では、既存株主の持ち株が引き続き維持されるため、新たに株式を発行しても議決権の100%取得はできません。
完全な経営支配を目指す場合は、株式譲渡を用いるか、第三者割当増資に加えて別の手法の併用を検討する必要があります。
2.株式譲渡に比べ多額の資金が必要
第三者割当増資で支配権を得るには、一定以上の新株を引き受ける必要があり、株式譲渡と比べて大きな資金負担が生じる場合があります。
株式譲渡では既存の発行済株式の中から必要な割合を取得すれば支配権を確保できますが、第三者割当増資では新しく株式を発行するため、既存株主の持株比率を考慮しながらより多くの株式を引き受ける必要があります。
結果、同じ議決権を得る場合でも、株式譲渡より資金負担が大きくなるケースが多いです。
第三者割当増資の手続きの流れ
第三者割当増資の発行手続きは、会社法により規定されていて、流れは以下のとおりです。
- 募集事項の決定
- 株主に対する通知・公告
- 引受け希望者に対する通知
- 引受けの書面を交付
- 割当先の決定と申込者への通知
- 出資の履行
- 株式の発行・登記変更
それぞれ説明します。
1.募集事項の決定
第三者割当増資を行うには、取締役会または株主総会の特別決議において募集事項を決定します(会社法201条1項、199条2項)。募集事項には以下の内容を含めます。
- 募集株式の数
- 株式の払込金額・算出方法
- 現物出資の場合は、その旨および内容・金額
- 払込期間や払込期日
- 増加する資本金や準備金
通常の発行であれば取締役会の決議で決定できますが、有利発行の場合は、株主総会の特別決議の承認を得る必要があります。
2.株主に対する通知・公告
募集要項を決定後は、払込期日または払込期間の初日の2週間前までに既存株主に募集事項を通知するか、公告を行わなければなりません(会社法201条3項、4項)。
3.引受け希望者に対する通知
募集要項を決定した後は、新株を申し込む引受希望者にも通知する必要があります(会社法203条1項)。
通知に記載する項目は、以下のとおりです。
- 株式会社の称号
- 募集事項
- 払込みの取扱いの場所
- その他法務省令で定める事項
会社の状況に応じて、会社法施行規則により追加の記載事項が求められる場合もあります。
4.引受けの書面を交付
通知を受け取った引受希望者は、以下の項目を記載した書面を発行会社に提出し、新株発行の申し込みを行います(会社法203条2項)。
- 申込みをする者の氏名や住所
- 引き受ける株式の数
書面を提出することで、正式に新株の引受けが申し込めます。
5.割当先の決定と申込者への通知
引受希望者から申し込みを受け付けた後、発行会社は誰に何株を割り当てるかを、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議で決定します(会社法204条1項)。
割当数が決定した後、会社は割り当てられた株式数を申込者に通知します。
6.出資の履行
割当を受けた引受人は、定められた払込期日または払込期間内に、会社が指定した銀行などの払込取扱場所で出資金の払い込みを行います(会社法208条1項)。
引受人が期限までに割当分の全額を払い込むことで、新たに発行された株式の株主としての権利が確定します。
もし引受人が期限内に払い込みを行わなかった場合は、株主となる権利は失効し、株式の取得は無効となります。
7.株式の発行・登記変更
企業は、増資が行われた日から2週間以内に、法務局で増資に関する登記を行う必要があります。
手続きには、資本金や発行株式数の増加を反映させる登記変更が含まれ、登記免許税の支払いと必要書類の提出が求められます。
第三者割当増資の株価へ与える影響
第三者割当増資が事業成長や拡大戦略の一環として実施される場合、市場から好意的に評価されることがあります。
例えば、新規事業の立ち上げや技術開発を目的とした資金調達であれば、将来的な成長が期待されて投資家にとって魅力的に映るでしょう。
また、割当先が関連事業を持っており事業提携によるシナジー効果が見込まれる場合は、企業価値の向上につながるため株価が上昇する可能性があります。
一方で、第三者割当増資に伴う株式の希薄化は株価下落の要因となるでしょう。新株発行によって発行済株式総数が増えると、1株あたりの価値が低下して既存株主の持株比率や配当が減少するため、株主が離れるリスクがあります。
とくに、市場価格を下回る価格で新株を発行する有利発行が行われると、既存株主の利益が損なわれるため、株価が下落するリスクが高まります。
第三者割当増資での株価の算定方法
第三者割当増資における新株の算定方法は、一般的な株価の算定方法と同様に、主に以下の3つの方法に分けられます。
算定方法 | 特徴 |
|---|---|
コストアプローチ | ・会社の保有している資産および負債を基準として評価する ・客観性が高いが、会社の業績や将来の収益価値を反映できない |
インカムアプローチ | ・将来の収益やキャッシュフローに対して、リスクを反映した割引率を 反映させて評価する ・会社の将来性を企業価値に含められるが、主観的な評価になりやすい |
マーケットアプローチ | ・譲渡対象企業と類似する企業の取引価格を参考に企業価値を評価する ・客観性に優れているが、類似企業の情報を探し出せるとは限らない |
株価の算定方法については「事業譲渡・株式譲渡の価値算定方法とは?価格に影響する要素も解説」にて解説しているので、併せて参考にしてください。
まとめ:第三者割当増資のメリット・デメリットを理解して検討しよう

今回は、第三者割当増資の仕組みや目的、手続きの流れ、メリット・デメリットを解説しました。
第三者割当増資は会社の資金調達方法のひとつであり、スピーディに資金調達ができるほか、他社との関係強化にも役立ちます。
一方で、株式の希薄化により既存株主が離れたり、株価が下がったりするリスクがあるため、メリット・デメリットを考慮した上で目的に合わせて進めることが重要です。
なお、弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また、シェアモルM&AのコラムにはM&A・事業承継関連の記事も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。
シェアモルM&Aでは無料相談を実施しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
■M&A・事業承継の仲介ならシェアモルM&A
最終更新日: 2025/3/4
まずは無料相談
ミーティング時に貴社とシナジーのあるクライアントの概要をお伝えいたします。
無料で事業価値の算定も可能でございますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
監修者
齋藤 康輔シェアモル株式会社 代表取締役
東京大学教養学部基礎科学科在学中に、半導体(シリコン)のシミュレーションを専攻する傍ら、人材会社にてインターン。
インターン中に人材会社向け業務システムを開発し、 大学卒業後の1年間、上記人材会社にて勤務後、 共同出資で2007年3月に上記システム「マッチングッド」を販売する会社、 マッチングッド株式会社を設立。
12年の経営の後、2019年1月に東証プライム上場企業の株式会社じげんに株式譲渡。
2019年9月、売却資金を元手に、シェアモル株式会社を設立。
自身のM&Aの経験から、買い主と売り主の間での情報の非対称性や、 M&A仲介会社が出している付加価値に疑問を感じ、 自身が思わず依頼したくなるような、 付加価値の高いM&A仲介サービスを提供したいと強く思い、 IT技術をフル活用したM&A仲介事業「シェアモルM&A」をスタート。
現在はシェアモルM&Aと、SEOに強い文章をAIが作成する「トランスコープ」を展開中。


