
M&Aノウハウ
最終更新日: 2025/1/13
【2025年】病院・クリニック業界のM&A・事業承継の動向と実態
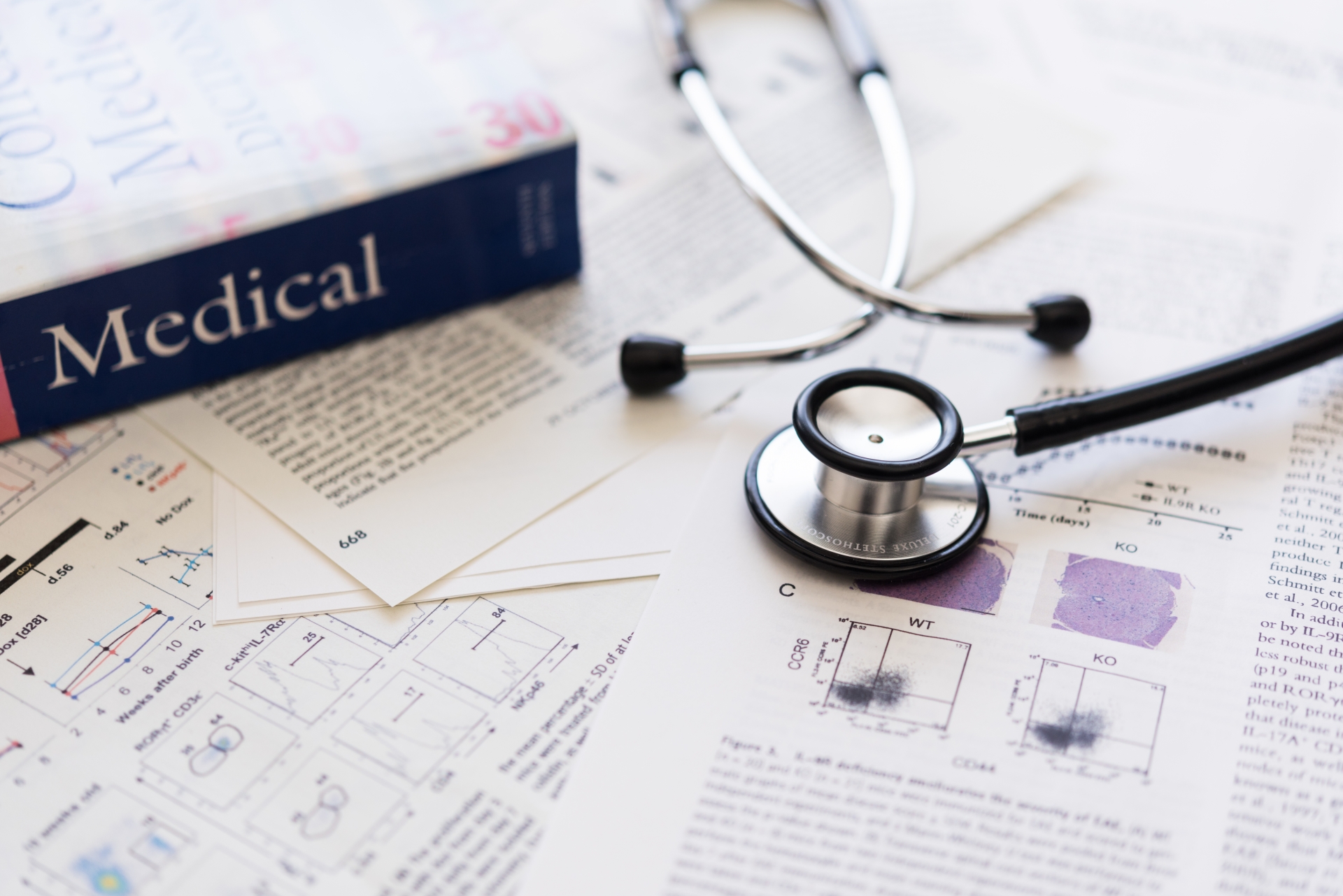
「病院やクリニックの事業承継の現状が知りたい」
「病院・クリニックにおけるM&Aのメリット・デメリットが知りたい」
このようにお考えではありませんか?
本記事では、病院・クリニックにおける事業承継・M&Aの現状や課題を解説するとともに、M&Aの流れやメリット、成功させるポイントを解説します。
ぜひ最後まで読んで、円滑に病院・クリニックのM&Aを進める参考にしてください。
なお、弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
病院・クリニックの事業承継・M&Aの現状と課題
病院・クリニック業界には以下のような課題があり、事業承継・M&Aは解決に向けた1つの手段として注目されています。
- 経営者の高齢化と後継者不足
- 休廃業・解散件数の増加
- 人手不足
それぞれ説明します。
1.経営者の高齢化と後継者不足
日本では、中小企業と同様に、病院・クリニック業界でも経営者の高齢化・後継者不足が進んでいます。
厚生労働省による2022年度の統計によると、病院の開設者・医療法人代表者の平均年齢は64.9歳、診療所の開設者・法人代表者の平均年齢は62.5歳と高い水準です。
また帝国データバンクによる後継者不在率の調査によると、病院・診療所は65.3%と全業種の中でも2番目に高く、全体の平均53.9%より10ポイント以上高い数値となっています。
医療業界における後継者問題の深刻化については、親族内承継の衰退も原因のひとつに挙げられます。
かつては、親子や親族間での承継が主流でした。
しかし、現代では医療への取り組み方や経営に関する方針の違いから、他の医療機関での勤務を選び、子や親族が後を継がないケースも多く見られます。
親から子へ病院経営が受け継がれるとは限らず、病院・クリニックの事業承継がより困難になっています。
2.休廃業・解散件数の増加
経営者の高齢化・後継者不足を受け、病院・クリニック業界では実際に休廃業・解散件数が増加しています。
帝国データバンクの調査によると、2023年度は休廃業・解散が709件確認されており、過去最多です。
休廃業の背景には、以下のような医療業界の難しい現状が影響していると考えられます。
- 医療体制の再編
- 人口減少による医療費の圧縮
- 医療業の収益性の低下
- 建物や設備投資費のコスト増加
地域医療体制の再編や医療環境の変化により、病院経営環境は今後も不透明な状況が続くとみられます。
3.人手不足
病院・クリニックの現場では、医師や看護師といった医療従事者の人手不足も深刻です。
医療現場では、医療法において人員配置基準が定められているため、入院患者数や入所者数に対して定められた必要配置人数が確保できなければ業務を縮小せざるを得ません。
とくに看護師については、看護基準の改定により7対1看護の基準を満たしていると診療報酬が高くなることから、採用競争が激化しています。
その他、医療従事者の不足の原因としては、高齢化社会における需要の増加に追いつかないことや職場環境の悪化などが挙げられます。
経営を安定させ、職場環境の改善・医療従事者の人員確保を進めることは、病院・クリニック業界の大きな課題と言えるでしょう。
病院・クリニック業界における事業承継の方法
病院・クリニック業界における事業承継の方法としては、以下の3つがあります。
- 親族事業承継
- 親族外事業承継
- M&Aを活用した事業承継
それぞれ説明します。
1.親族事業承継
親族事業承継とは、経営者が自分の親族に会社や事業を引き継ぐ手法です。
病院やクリニックの事業承継において、最初に検討されることの多い手法と言えます。
しかし、少子化や後継者は原則として医師に限られること、後継者候補との方針の違いなどにより、病院やクリニックの親族内事業承継は減少しています。
2.親族外事業承継
親族外事業承継とは、血縁関係のない第三者に事業を引き継ぐ手法です。
たとえば、親族ではない院内の医師などに事業を承継するケースが、親族外事業承継にあたります。
一般的に、該当の病院・クリニックで長期に渡って勤務している従業員を後継者とするため、方針や文化への理解が深く、既存の従業員や患者からも受け入れられやすい傾向にあります。
3.M&Aを活用した事業承継
親族事業承継や親族外事業承継が難しい場合には、病院・クリニックの事業承継の手段としてM&Aが活用されることも少なくありません。
M&Aを活用する場合は、専門の仲介会社や金融機関などのサポートを受けて広く譲渡先を探せるため、身近に後継者がいない場合でも自院を存続できる可能性が高まります。
病院・クリニックにおけるM&Aのメリット
病院・クリニックのM&Aにおける、売り手側・買い手側それぞれのメリットを見ていきましょう。
売り手側のメリット
病院・クリニックのM&Aにおける、売り手側のメリットは以下の5つです。
- 後継者問題の解消
- 地域医療の維持
- 経営基盤の安定化
- 従業員の雇用確保
- 売却益の獲得
それぞれ説明します。
1.後継者問題の解消
売り手側のメリットの1つ目は、後継者問題の解消です。
病院・クリニック業界では、経営者が高齢化する中、後継者の不在により存続が困難なケースが増加しています。
M&Aであれば専門の仲介会社の支援を受けて譲渡先を探せるため、後継者候補が身近にいない場合でも事業承継が実現でき、病院・クリニックの存続が可能です。
M&Aは事業を承継するひとつの手段として、後継者問題に悩む病院・クリニックに選ばれています。
2.地域医療の維持
売り手側のメリットの2つ目は、地域医療の維持です。
地域住民にとって病院・クリニックは必要不可欠な存在であり、簡単になくせるものではありません。
とくに、病院・クリニックが不足している地域では、1つの病院やクリニックが廃院しただけでも地域の人々に大きな影響を及ぼします。
M&Aを事業承継のひとつの手段として採用することで、地域医療を維持できる可能性が広がります。
3.経営基盤の安定化
売り手側のメリットの3つ目は、経営基盤の安定化です。
クリニックや規模の小さな病院では経営基盤が安定しづらく、職場環境の改善やより良い医療の提供が難しいケースもあります。
もし、M&Aが成功して大規模な医療法人の傘下に入ることができれば経営基盤の安定が図れ、さらにグループ内で連携して医療提供できるといったメリットも得られます。
4.従業員の雇用確保
売り手側のメリットの4つ目は、従業員の雇用確保です。
事業の存続が困難な場合、そのまま廃業してしまうと医師や看護師、事務スタッフの雇用継続ができなくなってしまいます。
しかし、M&Aで事業を承継できれば、在籍する従業員の雇用確保が実現できます。
5.売却益の獲得
売り手側のメリットの5つ目は、売却益の獲得です。
M&Aにより病院・クリニックを売却することで、売り手の経営者は売却益を得られます。
引退する経営者は高齢な場合も多く、獲得した利益は引退後の生活資金に利用が可能です。
買い手側のメリット
続いて、買い手側のメリットとしては、以下の5つが挙げられます。
- 医師・看護師等の確保
- コストを抑えた新規拠点の確保
- 診療領域の拡大・機能の多角化
- 専門性の強化
- 病床規制の回避
それぞれ説明します。
1.医師・看護師等の確保
買い手側のメリットの1つ目は、医師・看護師等の確保です。
近年、医師・看護師といった医療従事者の不足が問題となっている中、M&Aによって売り手の病院の医師・看護師等を引き継ぐことができるのは大きなメリットと言えます。
とくに看護師数を確保できると、診療報酬上のメリットも生じます。
医療従事者を新規で募集しても、優秀な人材が得られるとは限らず、即戦力の人材を確保できるのは魅力的でしょう。
2.コストを抑えた新規拠点の確保
買い手側のメリットの2つ目は、コストを抑えた新規拠点の確保です。
新しく病院・クリニックを立ち上げるには、設備投資や人材確保などに非常に多くの費用が必要です。
一方でM&Aにより既存の病院・クリニックを買収した場合には、売り手の設備や患者などを引き継ぎ、コストや手間を抑えて新しい拠点を手に入れられます。
また、既存の病院・クリニックには地盤ができているため、買収後は円滑に事業を展開できるのも魅力と言えます。
3.診療領域の拡大・機能の多角化
買い手側のメリットの3つ目は、診療領域の拡大・機能の多角化です。
M&Aにより今まで対応していなかった診療領域を確保できれば、診療領域を拡大し、病院としての機能も多角的に展開できます。
企業規模の拡大や、市場における存在感の強化にもつながり、経営上の大きなメリットとなるでしょう。
4.専門性の強化
買い手側のメリットの4つ目は、専門性の強化です。
自院で保有している診療領域と同じ領域の病院・クリニックを買収した場合には、経験豊富な医療スタッフ・専門の設備などを確保でき、専門性の強化につながります。
すでに自院で取り組んでいる領域でもあるので、買収後の展開をスムーズに進めやすいのも魅力です。
5.病床規制の回避
買い手側のメリットの5つ目は、病床規制の回避です。
病院・クリニックの新設時には、該当地域の都道府県知事などから許可を得た上で、医療計画に定められた病床規制に則って開設しなければなりません。
定められた基準病床数を超えた場合には許可が下りず、新規参入・事業拡大の妨げとなるケースもあります。
しかし、M&Aによって既存の病院・クリニックを買収すれば、規制を回避して比較的容易に病床を増やせます。
病院・クリニックのM&Aの流れ
病院・クリニックのM&Aの流れは、以下のとおりです。
- M&Aの検討・専門家への相談
- 交渉先探し
- トップ面談
- 基本合意契約書の締結
- 行政との調整
- デューディリジェンス
- 最終交渉・最終契約書の締結
- クロージング
おもな流れは、一般的なM&Aと同様です。M&Aの流れについて詳しくは、M&A・事業承継の流れを徹底解説!初回相談からクロージングまで!をご参考ください。
ただし、病院・クリニックのM&Aでは、買い手候補が決まってからM&Aを実行するまでに行政との調整が必要です。
行政との調整についてはM&A仲介会社のサポートも受けられるので、相談しながら進めるとよいでしょう。
病院・クリニックのM&Aを成功させる7つのポイント
病院・クリニックのM&Aを成功させるためには、以下の7つのポイントを意識しましょう。
- 開設手続きを確認する
- 許認可の引き継ぎに注意する
- 行政とコミュニケーションをとる
- 医師・看護師の流出を防ぐ
- 適したM&Aスキームを選ぶ
- 買い手探しに力を入れる
- M&Aの専門家に相談する
それぞれ説明します。
1.開設手続きを確認する
ポイントの1つ目は、開設手続きを確認することです。
病院・クリニックは許可制の事業であり、開設する際には1つひとつの手続きが重要です。
たとえば、病院の開設主体は公的部門(国、自治体など)と民間部門(医療法人・社会福祉法人・公益法人・個人など)に大別され、さらに民間部門の中でもそれぞれに手続き方法が異なります。
円滑にM&Aを進めるために、開設手続きについてあらかじめよく確認しておきましょう。
2.許認可の引き継ぎに注意する
ポイントの2つ目は、許認可の引き継ぎに注意することです。
個人経営の病院・クリニックは個別に資産を売却するため、そのままでは許認可は引き継がれません。
許認可がうまく引き継がれないせいで運営に支障が出ないよう、引き継ぎの完了日から逆算して申請や引き継ぎのスケジュールを立てておきましょう。
3.行政とコミュニケーションをとる
ポイントの3つ目は、行政とコミュニケーションをとることです。
病院・クリニックのM&Aにおいて、M&A後に後継者が事業を再開するためには、管轄行政の許可が必要です。
そして、地方自治体によって許可要件は異なる部分もあり、円滑な再スタートには管轄行政とのコミュニケーションが欠かせません。
スムーズに事業を再開できるよう、十分に時間をかけて、管轄する行政とコミュニケーションをとっておきましょう。
4.医師・看護師の流出を防ぐ
ポイントの4つ目は、医師・看護師の流出を防ぐことです。
売り手の病院やクリニックで働く医師・看護師といった人的資産を獲得することは、買い手側にとってM&Aの大きな目的のひとつです。
しかし中には、経営者が変わることへの不安・雇用条件の変更への不満などによって、医師・看護師が退職してしまうケースも見られます。
スタッフの流出は患者の離脱につながる恐れもあるため、M&A実行の際は早めにスタッフとコミュニケーションを取り、十分に関係を構築するなどの対策が重要です。
5.適したM&Aスキームを選ぶ
ポイントの5つ目は、適したM&Aスキームを選ぶことです。
病院・クリニックには、一般企業とはM&Aスキームが異なる部分があり、たとえば株式が存在しないため株式譲渡は行えません。
反対に、医療業界に固有なものとしては、医療法人理事の交代・出資持ち分の譲渡といったスキームがあります。
事業譲渡や合併と合わせて、取り得る方法の中から自院にとって最適なスキームを選ぶことは、M&Aの成功に欠かせません。
サポートを依頼する専門業者のアドバイスも取り入れ、しっかりと検討しましょう。
6.買い手探しに力を入れる
ポイントの6つ目は、買い手探しに力を入れることです。
病院・クリニックは許可制の事業であり、買い手は運営母体が医療法人に限られるため、かなり限定的になります。
そのため、M&Aを成功させるためには、取引相手候補は決して多くないことを前提に、買い手探しには十分に力を入れる必要があります。
7.M&Aの専門家に相談する
ポイントの7つ目は、M&Aの専門家に相談することです。
病院・クリニックのM&Aでは買い手探しから最適なスキームの選択、行政との調整など、専門家のサポートを必要とする場面が多くあります。
M&Aを円滑に進めるためにも専門家への相談が欠かせず、相談先の選定はM&Aの成功を左右する大きな要因と言えます。
M&Aの相談先の選び方について詳しくは、無料で相談可能?M&A・事業承継のオススメ相談先や相談方法とは?をご参考ください。
病院・クリニックのM&Aの売却相場
病院やクリニックの売却価格の目安は、以下のとおりです。
病院・クリニックの売却相場 = 純資産+営業権(直近の利益の2~5年分)
総資産から負債を除いた純資産に、営業権(のれん代)を加えた合計金額が譲渡価格の目安となります。
営業権は、直近の営業利益の2〜5年分が相場です。
また、以下のような要因も、病院・クリニックの売却相場に影響します。
- 知名度
- 患者数
- 立地
- 優秀なスタッフの有無
M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)の算定方法については、事業譲渡・株式譲渡の価格算定方法とは?価格に影響する要素も解説をご参考ください。
病院・クリニックのM&Aの事例
ここからは、病院・クリニックのM&Aの事例について公正取引委員会の資料「医療法人(病院)のM&Aの実態」を元に紹介します。
事例①
【概要】
・売り手側の医療法人は、埼玉県にて30年以上、精神病院経営を運営
・娘は医者だが、後を継ぐ気はなし
・2年前に後継者として外部から医師を招いたものの、方針の違いにより夜逃げ
・後継者不在に悩まされていたが、売り手側の関東進出ニーズと合致し、スピーディにM&Aが成立
売り手側 | 買い手側 | |
|---|---|---|
所在地 | 埼玉県 | 愛知県 |
事業内容 | 精神病院経営(約100床) | 精神病院経営(約300床) |
経営者の年齢 | 65歳 | 47歳 |
M&Aの理由 | 後継者の不在 | ・関東への進出 ・精神病床の獲得 |
売り手側の後継者問題と、買い手側の事業拡大のニーズが合わさり、スムーズなM&Aが実現した事例です。
買い手側は、精神病院という同じ領域の買収により、専門性の強化や関東への新規拠点の獲得に成功しています。
事例②
【概要】
・売り手側の医療法人は、埼玉県にて30年以上、慢性期病院を運営
・息子は医師だが、病気のため働ける状況ではない
・常勤の勤務医師達も、承継する意思はなし
・後継者不在に悩まされていたが、売り手側の関東進出ニーズと合致しM&Aが成立
売り手側 | 買い手側 | |
|---|---|---|
所在地 | 埼玉県 | 北海道 |
事業内容 | 病院・介護施設経営 | 病院・介護施設経営 |
経営者の年齢 | 75歳 | 70歳 |
M&Aの理由 | 後継者の不在 | ・関東への進出 ・訪問医療への相乗効果 |
買い手側は、北海道にて再生病院の請負からスタートし、わずか10年で1,000床を有する規模に成した医療法人です。
東京でも訪問医療を中心としたクリニックを複数展開しており、売り手の病院を拠点の1つとしたい意向によりM&Aが成立しました。
事例③
【概要】
・売り手側の医療法人は、地元高齢者が対象の訪問診療クリニックを上野と町屋の2か所で運営
・初代理事長の急逝により、2年前より非医師の兄が理事長を務めていたが、一族に医師はおらず後継者問題を抱えていた
・売り手側の訪問診療への進出・事業領域の拡大のニーズと合致しM&Aが成立
売り手側 | 買い手側 | |
|---|---|---|
所在地 | 東京都 | 千葉県 |
事業内容 | クリニック経営(2施設) | 医科・歯科経営(広域医療法人) |
経営者の年齢 | 72歳 | 55歳 |
M&Aの理由 | 後継者の不在 | ・訪問診療(医科への進出) ・事業領域の拡大 |
今回のケースでは、買い手側は全国で訪問歯科診療を展開する、M&Aに積極的な医療法人でした。
訪問歯科診療分野と、売り手側の特徴である訪問診療分野との相乗効果を狙い、後継者不在に悩む売り手側とのM&Aが成立しています。
まとめ:専門家のサポートで円滑に病院・クリニックのM&Aを進めよう

今回は、病院・クリニックにおける事業承継・M&Aの現状や課題を解説するとともに、M&Aの流れやメリット、成功させるポイントを解説しました。
高齢化や後継者不在が進む中、M&Aによる事業承継は病院・クリニックを存続させる有効な手段のひとつと言えます。
ぜひ、本記事を参考に、スムーズなM&A・事業承継を進めていただければと思います。
なお、弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また、シェアモルM&AのコラムにはM&A・事業承継関連の記事も掲載しておりますので、併せてご覧ください。
シェアモルM&Aでは無料相談を実施しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
最終更新日: 2025/1/13
まずは無料相談
ミーティング時に貴社とシナジーのあるクライアントの概要をお伝えいたします。
無料で事業価値の算定も可能でございますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
監修者
齋藤 康輔シェアモル株式会社 代表取締役
東京大学教養学部基礎科学科在学中に、半導体(シリコン)のシミュレーションを専攻する傍ら、人材会社にてインターン。
インターン中に人材会社向け業務システムを開発し、 大学卒業後の1年間、上記人材会社にて勤務後、 共同出資で2007年3月に上記システム「マッチングッド」を販売する会社、 マッチングッド株式会社を設立。
12年の経営の後、2019年1月に東証プライム上場企業の株式会社じげんに株式譲渡。
2019年9月、売却資金を元手に、シェアモル株式会社を設立。
自身のM&Aの経験から、買い主と売り主の間での情報の非対称性や、 M&A仲介会社が出している付加価値に疑問を感じ、 自身が思わず依頼したくなるような、 付加価値の高いM&A仲介サービスを提供したいと強く思い、 IT技術をフル活用したM&A仲介事業「シェアモルM&A」をスタート。
現在はシェアモルM&Aと、SEOに強い文章をAIが作成する「トランスコープ」を展開中。


