
M&Aノウハウ
最終更新日: 2025/1/13
M&A・事業承継の問題とは?現状の課題から対策方法を徹底解説
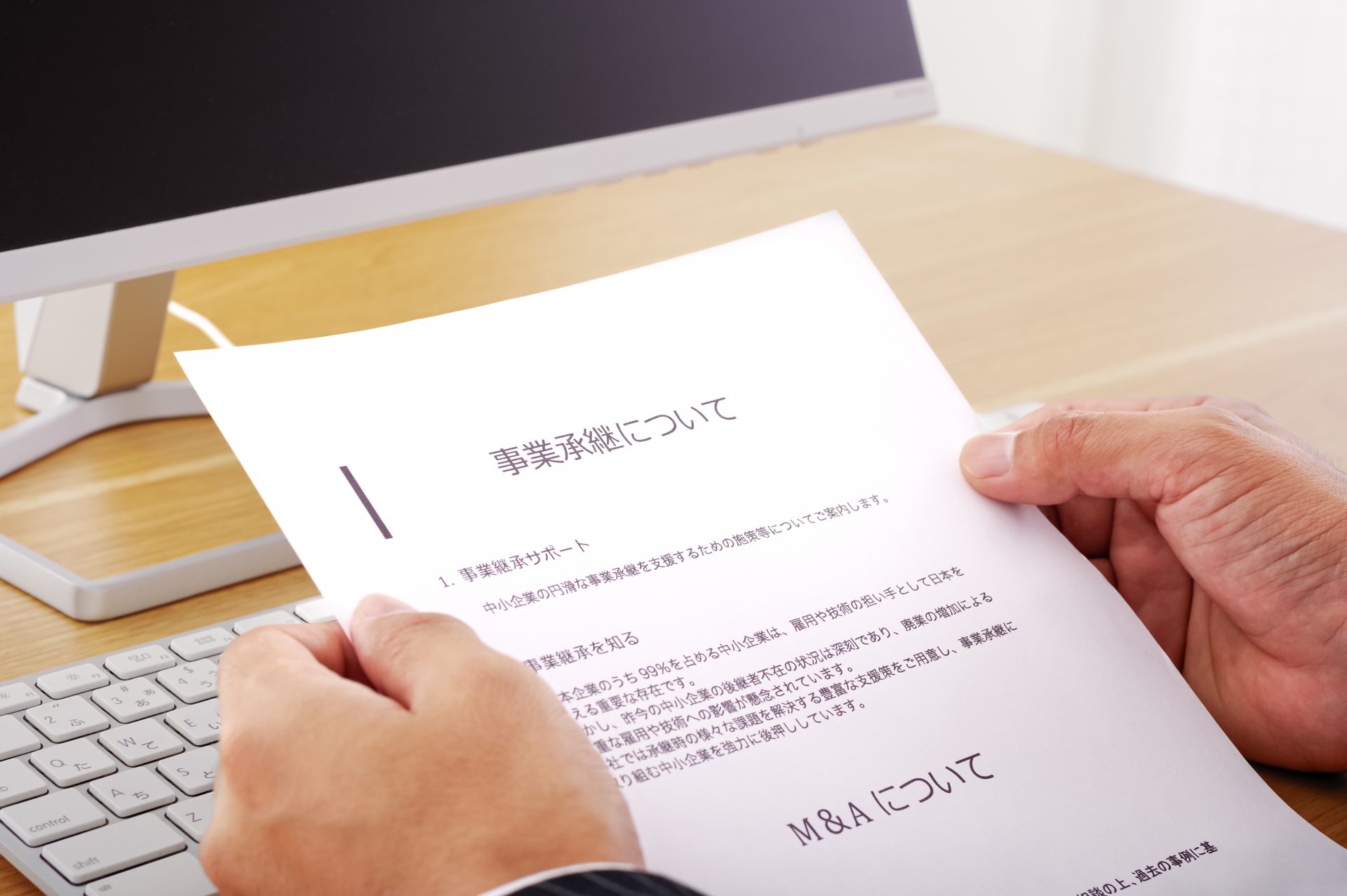
「M&A・事業承継にはどのような問題がある?」
「課題と対策方法について知りたい」
M&Aや事業承継を検討中の経営者は、上記のようにお悩みではありませんか。
本記事では、M&A・事業承継の問題と現状について徹底解説します。
また、対策方法も丁寧に解説するため、M&A・事業承継をスムーズに進めたい方はぜひ参考にしてください。
なお、シェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
M&A・事業承継における8つの問題と現状
M&A・事業承継の問題として、下記の8つが挙げられます。
- 経営者の高齢化
- 後継者不足
- 個人保証の引継ぎ
- 株式・事業用資産の買取
- 税負担
- 雇用の維持
- 取引先との関係
- 経営交代後の業績
具体的なデータを参考にしながら、解説します。
1.経営者の高齢化
日本政策金融公庫によれば、経営者の平均年齢は2004年時点で57.97歳から、2023年には62.33歳と上昇傾向です。
経営者の年齢が上がるにつれて、廃業を視野に入れている企業も多くなり、小規模や業績が低迷している企業も多い傾向です。
経営者の高齢化問題は、廃業だけでなく経営者本人の健康面・体力面で時間的な猶予がない課題もあります。
日々の業務をこなす合間で、後継者探し・育成しなければならないため、高齢の経営者ほどM&A・事業承継の負担は重いです。
日本が超高齢化社会に突入する「2025年問題」もあり、事業承継の重要性が一層高まっているといえるでしょう。
2.後継者不足
中小企業白書(2024年版)によると、後継者不在率は全体で54.5%です。
経営者の年齢で見ると、70代は29.5%、80代でも23.1%で「後継者がいない」と回答しています。
後継者不足は廃業に至る点のみならず、従業員が職を失い、築き上げた技術・ノウハウまで失われるのも大きな問題です。
たとえば、伝統工芸職人において後継者が不足し続けて技術も一度失われると、新たに生産するのは非常に困難であると考えられます。
しかし、後継者が決定している企業においても、承継に関する課題を抱えているところもあります。
3.個人保証の引継ぎ
個人保証(経営者保証)とは、経営者が連帯保証人となり金融機関の融資を受けられる制度です。
中小企業やベンチャー企業が金融機関から融資を受けようとすると、個人保証を要求されます。
経営者個人が保証人となることによって、金融機関側は未収・貸し倒れリスクを軽減でき、経営者側は融資を受けやすくなります。
ところが事業承継においては、個人保証も引き継ぐことになるため、後継者の負担が増大する点も問題です。
経営状況によっては個人保証の影響から、負債を抱えるリスクが高い印象を与えてしまうため、後継者が決まりにくい原因の1つとなるでしょう。
4.株式・事業用資産の買取
中小企業白書(2024年版)によると、すでに後継者が決定している企業でも、問題になりそうなこととして「株式・事業用資産の買い取り(22.5%)」を3位に挙げています。
株式譲渡では、対象企業の純資産が多いほど株価も高額になるため、後継者側は多額の買収資金を用意する必要があります。
自己資金で用意できなければ、金融機関からの借り入れなどをして、資金調達する必要も出てくるでしょう。
また、株式譲渡では資産・負債ともまとめて承継するため、不要な資産や簿外負債なども引き継ぐ可能性があります。
後継者にとっては、株式や事業用資産を買い取るための資金調達・負債のリスクが課題です。
5.税負担
事業承継することによって、相続税や贈与税の負担も課題となります。
中小企業白書(2024年版)では、「相続税・贈与税の問題(22.9%)」は事業承継で問題になりそうなことの2位でした。
国税庁公式サイトより、相続税と贈与税の速算表を下記に掲載するので、参考にしてみてください。
【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【贈与税の速算表(特例贈与財産用)】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
株式や事業用資産の買い取りだけでなく、税負担まで発生すれば、事業承継に後ろ向きとなる可能性も高まるでしょう。
6.雇用の維持
事業承継で経営者が交代したあとの、雇用を維持するのも課題として挙げられます。
日本政策金融公庫によれば、引き継いでもらいたい経営資源の2位が「従業員(27.0%)」です。
従業員にとっては、経営者が交代したあとの経営方針・雇用条件に変更がないか心配します。
また、後継者への不満や条件などの変化によって、退職に繋がる従業員も出てくるでしょう。
これまで大切にしてきた従業員に対し雇用を維持してもらいたい、と考える経営者は多いといえます。
7.取引先との関係
経営者と取引先の関係性が強い場合、事業承継後に影響を与える可能性もあるでしょう。
中小企業白書(2024年版)によると、後継者は決定している企業が事業承継で問題になりそうなことに「取引先との関係の維持(18.5%)」を4位に挙げています。
たとえば、信頼関係をゼロから築いていく必要があったり、取引先の後継者に対する懸念や疑念があったりします。
経営者側も、後継者へ引き継ぐことによって取引先に不便をかけてしまわないか、契約を破棄されないか気がかりでしょう。
8.経営交代後の業績
後継者が見つかったから事業は安泰、というわけではありません。
後継者の経営能力が未熟であれば、業績不振に陥る可能性もあります。
特に、創業者である経営者から、2代目に代替わりするケースでよく見られます。
業績不振に陥る原因は、引き継ぎが不十分であったり後継者の経営力不足であったりするなど、さまざまです。
M&A・事業承継は課題がさまざまであるため、企業の状況に合わせて柔軟に対応し、解決しなければいけません。
M&A・事業承継の課題解決策8選
ここからは、M&A・事業承継8つの課題に対する解決策を解説します。
- 経営者の高齢化
- 後継者不足
- 個人保証の引継ぎ
- 株式・事業用資産の買取
- 税負担
- 雇用の維持
- 取引先との関係
- 経営交代後の業績
それぞれ見ていきましょう。
1.経営者の高齢化
経営者が高齢になるにつれて、ある日突然、経営の指揮を取れなくなる場合も考えられます。
そのため、早期に後継者候補を決定し、育成するのがおすすめです。
事業内容によって、引き継ぎに必要な期間は変わります。
たとえば、伝統工芸技術を引き継ぐならば何年も修行して習得する必要があり、10年以上かかることもあるでしょう。
年齢や時間は戻せないため、事業を存続させたいと考える経営者ほど、後継者探しや育成に注力する必要があります。
2.後継者不足
後継者の探し方には、以下の方法がおすすめです。
- M&A仲介会社に探してもらう
- 事業承継・引継ぎ支援センターで探す
- 親族・従業員から探す
- 後継者マッチングサイトで探す
特に、M&A仲介会社では後継者探しから交渉・契約など、幅広いサポートを受けられます。
弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また後継者がいない!後継者の探し方・決め方の記事は、後継者不足に悩む経営者向けに解決策などを解説しておりますので、併せてご覧ください。
3.個人保証の引継ぎ
個人保証(経営者保証)の問題を解決するには、以下の取り組みが必要です。
- 個人保証の解除
- 個人保証の分散
個人保証があることで事業承継を進められない企業もあるため、解除や分散できれば承継もスムーズです。
全国銀行協会が「経営者保証ガイドライン」を制定しているため、内容を十分確認しましょう。
ガイドラインを活用して一定の条件を満たすことで、後継者が個人保証を引き継がずに事業承継できたり、破産せずに保証債務を整理することも可能です。
経営者個人で進めるのは難しいため、M&Aアドバイザーや弁護士などの専門家へ相談するのがおすすめです。
4.株式・事業用資産の買取
後継者が株式や事業用資産を買い取るための資金調達方法として、以下を活用できます。
- 補助金などの公的支援制度
- 事業承継ローン
支援制度として、事業承継・引継ぎ補助金(M&A補助金)があり、事業の継続・成長を目的としています。
補助対象となる取組内容・経費に応じて種類があり上限額も異なるため、企業ごとに合わせた詳しい活用方法に関しては、M&Aアドバイザーや司法書士などのサポートを受けましょう。
なお、補助金の詳細は事業承継・引継ぎ補助金(M&A補助金)の概要と申請方法解説にて、解説しています。
また、株式譲渡の詳細は事業譲渡・株式譲渡の価格算定方法とは?価格に影響する要素も解説にて解説しているため、併せてご覧ください。
5.税負担
事業承継する際の相続税・贈与税の負担を軽減する対策について、猶予を受けられる事業承継税制を活用するのがおすすめです。
事業承継税制を活用すれば、下記のメリットを受けられます。
- 事業承継の際に税負担を軽減
- 一定の条件を満たせば納税免除
- 事業承継時の株価対策が不要
- 事業用資金に回せるリソースを確保
事業承継税制は後継者の税負担を軽減でき、後継者不足に悩む経営者にとっても助けとなります。
事業承継税制の詳細は事業承継税制とは?制度の内容や要件、メリットから注意点まで解説!を併せてご覧ください。
6.雇用の維持
事業承継後も雇用を維持することによって、従業員が安心して働き続けられます。
現状の雇用・待遇は維持する旨を従業員に周知し、変更せざるを得ないときは、必要に応じて個別で対応する場を設けるのも大切です。
経営者交代とともに、経営方針や待遇の変化に対して、不安に思う従業員もいるでしょう。
事業承継税制においては「雇用確保要件」として、事業承継後5年間は平均8割以上の雇用を維持しなければならず、達成できなかった場合は猶予された税金を納める必要があります。
退職する従業員が多ければ、納税だけでなく採用活動のリソースも増えてしまうため、雇用を維持することは重要な課題です。
7.取引先との関係
経営者が交代することによって、取引先との関係に影響する場合もあります。
取引先と良好な関係を維持するためには、承継前に経営者交代の時期や後継者を紹介するなど、事前に説明しておくと理解を得られやすいでしょう。
ただしM&Aの場合、情報漏洩のないよう慎重に進める必要があります。
取引先に伝えるタイミングに関しては、専門家と相談するのがおすすめです。
8.経営交代後の業績
経営者が交代後に、業績不振に陥るケースは珍しくありません。
引き継いで終わりではなく、事業承継後も何年と続けられるよう、中長期的に計画を立てる必要があります。
また、承継前に後継者教育を徹底することで、経営能力を高められるでしょう。
後継者による経営が軌道に乗るまでは、必要に応じてサポートしたり、専門家を活用したりするのがおすすめです。
サポートしてくれる人がいて相談できる環境であれば、後継者にとっても引き継ぎ後の不安を減らせるでしょう。
M&A・事業承継の課題解決に専門家を活用すべき理由
M&A・事業承継の課題解決には、専門家の活用をおすすめします。
なぜなら、M&A・事業承継を実施するには、以下のような専門知識が必要だからです。
- 法務:売買契約書・株式譲渡契約書などの作成
- 税務:事業承継に伴う相続税・贈与税の節税対策
- 財務:財務諸表の分析やキャッシュフローを予測
- 人事・労務:従業員の管理や労務管理
経営者が1人で全てを正しく把握し、通常業務もある中で事業承継するのは負担が大きくなります。
また、企業によって抱える課題や必要物は異なるため、手続きが複雑かつ時間もかかります。
さらに後継者と交渉する際、第三者である専門家が間に入ることで、客観的に評価できトラブルのリスクも軽減可能です。
専門家を活用することで負担を軽減でき、M&A・事業承継を円滑に進められます。
M&A・事業承継における課題解決の頼れる相談先8選
M&A・事業承継における課題解決として頼れる相談先は、下記の8つです。
- M&A仲介業者
- ファイナンシャル・アドバイザー
- 金融機関
- 公認会計士・税理士
- 弁護士
- 商工会議所
- 事業承継・引継ぎ支援センター
- 経営者仲間・知り合い
どの分野でサポートしてもらえるか、解説します。
1.M&A仲介業者
M&A仲介業者は、売り手企業と買い手企業の橋渡し役として、交渉の仲介・助言を行います。
一貫支援を提供しており、M&A・事業承継を円滑に進行できる点や、双方の希望に合わせたマッチングも可能な点がメリットです。
M&A仲介業者の中には、成約までに着手金・中間金が発生するサービスもあるため「完全成功報酬型」を選ぶのをおすすめします。
弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また、シェアモルM&Aは「完全成功報酬型」であり、成約まで費用を請求いたしません。
無料相談を実施しておりますので、気になった方はこちらより、お問い合わせください。
2.ファイナンシャル・アドバイザー
ファイナンシャル・アドバイザー(FA)は、売り手企業か買い手企業のどちらかと専属契約し、M&Aの交渉をサポートします。
上場企業のような大手M&A案件において利用されることが多く、自社の利益を最大化させるためにFAは強い味方となります。
しかし、大型案件で利用されており、中小企業は対応外としているところもあるため、注意が必要です。
上場企業で後継者探しに難航しているのであれば、FAの活用をおすすめします。
3.金融機関
金融機関は、資金調達や融資に関する相談先として適しています。
企業との取引実績もあり、特にM&A専門部署のある金融機関は、専門性の高いサポートがメリットです。
FAと同じく大型の案件が主であり中小企業は対応外とする点や、アドバイザリー形式で費用が高額な傾向もある点はデメリットです。
上場企業で、特に資金調達・融資に関するアドバイスを希望するのであれば、金融機関への相談をおすすめします。
4.公認会計士・税理士
公認会計士や税理士は、財務・税務の専門知識を活かして、下記のサポートをします。
- 税務対策:相続税・贈与税の負担軽減対策
- 財務分析:企業の財務状況を分析し、適切な事業承継計画を策定
- 会計監査:財務状況の透明性を確保するために監査を実施
M&A・事業承継においてデューデリジェンスを実施することは、後継者からの信頼性を高め、交渉をスムーズに進めるためにも重要です。
顧問会計士・税理士であれば、信頼関係がすでにあり、自社の会計・税務状況も把握できているため効率的です。
公認会計士・税理士によってはM&Aは対応外としていたり経験が十分でなかったりすることから、事前にサポート範囲を確認しておきましょう。
5.弁護士
弁護士は、法的な観点でM&Aや事業承継の下記についてサポートします。
- 契約書作成:売買契約書や株式譲渡契約書の作成・確認
- 法務リスクの管理:法務リスクを最小限に抑えるためのアドバイス
- トラブル解決:事業承継に伴うトラブル解決を支援
顧問弁護士であれば、すでに信頼関係があるため、法律関連の相談をしやすいでしょう。
もしM&A・事業承継の支援を専門としていない場合、ノウハウ・経験不足の可能性があります。
無料相談を実施する弁護士事務所もあるため、相談してみて信頼できそうな弁護士に依頼するのがおすすめです。
6.商工会議所
商工会議所は、地域の企業支援を行う公的機関です。
下記のようなM&A・事業承継に関する情報提供や、各種相談に対応しています。
- 情報提供:事業承継やM&Aに関する情報提供
- セミナー開催:M&A・事業承継に関するセミナーやワークショップを開催
- 専門家紹介:必要な専門家(弁護士、公認会計士、税理士など)を紹介
商工会議所は中小企業の支援経験が豊富で、外部との連携もスムーズです。
しかし、M&A・事業承継の専門機関ではないため、手続きなどのサポートは受けられないことが多いです。
M&A・事業承継の基本を知りたい方や、公的な支援制度・支援機関を教えてほしい方は、商工会議所を頼ると良いでしょう。
7.事業承継・引継ぎ支援センター
事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する公的機関です。
M&A・事業承継に必要な、下記の支援を実施しています。
- 情報提供
- アドバイス
- 専門家の紹介
- 後継者のマッチング
各都道府県にセンターがあるため、地方企業も利用しやすいのが魅力です。
令和4年度の支援実績は、成約譲渡企業のうち約7割が、従業員数10名以下の小規模企業でした。
センターの利用は無料ですが、紹介された専門家と契約する場合は、費用が発生する場合もあります。
中小企業・地方企業で、公的機関に相談したい場合は、事業承継・引継ぎ支援センターを活用しましょう。
8.経営者仲間・知り合い
経営者仲間や知り合いに頼れば、実際の経験に基づいたアドバイスを提供してくれます。
M&A・事業承継のリアルな話や、「あれは失敗した」「これはやめておけ」などのネガティブな情報も聞けるでしょう。
また、M&Aや事業承継に詳しい人物への紹介も期待できます。
ただし、専門的な知識・アドバイスは難しく情報漏洩のリスクもあるため、相談相手は見極める必要があります。
なお相談先を選ぶポイントや費用については、無料で相談可能?M&A・事業承継のオススメ相談先や相談方法とは?で解説しているため、併せてご覧ください。
まとめ:M&A・事業承継における課題は専門家へ相談しよう

M&A・事業承継には多くの課題があり、すぐに解決できない問題もあります。
税務や法務など、必要な専門知識と範囲は広いため、経営者の負担軽減・業務効率化するためにも専門家の活用がおすすめです。
M&AアドバイザーのいるM&A仲介業者であれば、売り手企業と買い手企業の橋渡し役として、一貫支援を提供しています。
なお、弊社のシェアモルM&Aは、
- 最低成果報酬を抑えた完全成果報酬型
- AIを活用した提案力
- 豊富な経験と知識によるリスクの低減
- クローズドで丁寧な進行
の4点で、他社様から選ばれております。
また、弊社コラムにはM&A・事業承継関連の記事も掲載しておりますので、併せてご覧ください。
シェアモルM&Aでは無料相談を実施しておりますので、こちらよりお気軽にお問い合わせください。
最終更新日: 2025/1/13
まずは無料相談
ミーティング時に貴社とシナジーのあるクライアントの概要をお伝えいたします。
無料で事業価値の算定も可能でございますので、まずはお気軽にご相談いただけましたら幸いです。
監修者
齋藤 康輔シェアモル株式会社 代表取締役
東京大学教養学部基礎科学科在学中に、半導体(シリコン)のシミュレーションを専攻する傍ら、人材会社にてインターン。
インターン中に人材会社向け業務システムを開発し、 大学卒業後の1年間、上記人材会社にて勤務後、 共同出資で2007年3月に上記システム「マッチングッド」を販売する会社、 マッチングッド株式会社を設立。
12年の経営の後、2019年1月に東証プライム上場企業の株式会社じげんに株式譲渡。
2019年9月、売却資金を元手に、シェアモル株式会社を設立。
自身のM&Aの経験から、買い主と売り主の間での情報の非対称性や、 M&A仲介会社が出している付加価値に疑問を感じ、 自身が思わず依頼したくなるような、 付加価値の高いM&A仲介サービスを提供したいと強く思い、 IT技術をフル活用したM&A仲介事業「シェアモルM&A」をスタート。
現在はシェアモルM&Aと、SEOに強い文章をAIが作成する「トランスコープ」を展開中。


